
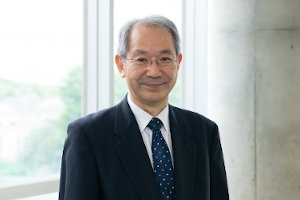
「人間とは何か」を問い続ける大学
田園調布学園大学は、人間福祉学部・子ども教育学部・人間科学部の三学部、そして大学院の人間学研究科からなる大学です。子ども教育学部の「子ども」はいうまでもなく、人間の子どもですから、学部・研究科の名称すべてに「人間」を冠しているといってもよいでしょう。このことは、本学が常に「人間」を問題にしていることを意味しています。
本学は、これまで社会福祉士や保育士などの多くの専門職を輩出してきましたので、資格に強い大学という評価を受けています。もちろん大学で資格を取得することは重要なことなのですが、本学で取得できる資格は、人間に深く関わる資格であるだけに、「人間とは何か」を問うことが必須の事柄になっています。本学では単に資格取得をめざすだけでなく、その根源にある「人間」を問う姿勢を大切にしています。
この「人間とは何か」という問いを考えるにあたって、本学の建学の精神である「捨我精進」はその一助となるものです。約100年前に川村理助先生が提唱した「捨我精進」を現代に生きる私たちはどのように理解すればよいのでしょうか。その答えは簡単ではありません。しかし、「捨我精進」とは何かを考えていくことは、「人間」と考えることに通じます。
私たちは、「人間」にこだわった教育を展開していこうと考えています。引き続き皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。

| 学歴・職歴 |
1983年 慶應義塾大学大学院社会学研究科教育学専攻(博士課程)単位取得満期退学 1989年 慶應義塾大学教職課程センター助教授 1998年 慶應義塾大学教職課程センター教授 2008年 慶應義塾福澤研究センター所長
2021年 慶應義塾大学名誉教授 2023年 田園調布学園大学副学長 |
|---|---|
| 論文・著書 |
『民衆の感じる痛みに応えようとして生まれた自由大学』(共編著)、エイデル研究所、2024年 『よくわかる生涯学習(改訂版)』(共著)、ミネルヴァ書房、2016年 『社会教育の基礎』(共著)、学文社、2015年 『近代日本と福澤諭吉』(共著)、慶應義塾大学出版会、2013年 『福澤諭吉事典』(共編)、慶應義塾、2010年 『慶應義塾史事典』(共編)、慶應義塾、2008年 『応用倫理学講義6 教育』(共著)、岩波書店、2005年 「福澤諭吉・慶應義塾から官・公・私立学校の別を考える」、『近代教育フォーラム』第24号、教育思想史学会、2015年 |
| 所属学会 |
教育史学会 全国地方教育史学会 日本社会教育学会 生涯学習・社会教育研究促進機構 |
| 社会活動 |
世田谷市民大学評議員 一般社団法人福澤諭吉協会理事 |

「共感」し「思いやる」ことの大切さ
本学は、少人数教育を重視し、学生一人ひとりを大切にする教育を長年にわたり実践してきました。教員と学生の距離が近く、きめ細やかな指導・助言が行き届く環境は、本学の大きな特色であり、学生の皆さんがそれぞれの夢に向かって成長していくための力強い支えとなっています。
また、神奈川県内トップクラスの就職率を誇る本学は、卒業生の社会での活躍を通じて、地域社会から厚い信頼を得ています。この実績は、学生一人ひとりの努力はもちろんのこと、教職員が一丸となって築き上げてきた成果であり、私もその一員としてさらに力を尽くしてまいります。
少子高齢化が急速に進む社会において、社会福祉、子ども教育、心理学の専門知識を持った人材の重要性はますます高まります。そうした時代のニーズに応え、田園調布学園大学は、地域社会や国際社会に積極的に貢献できる人材の育成を使命とし、教育・研究活動のさらなる充実に努めてまいります。
加えて、私は、人が人を思いやる気持ちの大切さを強く感じております。私たちには、他者の気持ちに寄り添い、共感し、思いやる力が備わっています。この思いやりは、社会での人間関係を豊かにし、信頼や協力を築くために不可欠な力です。私は、この思いやりの醸成を、本学の教育の中でも大切にしたいと考えています。
特に、川崎市をはじめとする地域社会との連携を強化し、地域福祉や子育て支援、学校教育の現場における課題解決に貢献できる取り組みを積極的に推進していきたいと考えております。
学生の皆さんが充実した学生生活を送り、社会で活躍できる人材へと成長できるよう、共に捨我精進してまいります。

人と共に生きる人間力を ― 春に思う
春は、様々な姿を私たちに見せてくれます。
陽春、春風、春霞、春一番、春嵐、春寒、そして春告鳥に桜。
自然の移ろいは私たちの歩みにも似て、心地良い陽射しの中で仲間と共に穏やかに過ごす時があれば、予期せぬ出来事に右往左往する時もあります。
春は、新入生を迎え、また学生たちもそれぞれに進級し、心あらたまる時でもあります。大学の4年間を人生の季節に準えると、いったいどのような季節が巡ってくるのでしょう。 例え、どのような季節に出合おうとも、学生、教員共に「自己と他者、そして私たちが生きる社会」について、福祉、保育、教育という専門性を通して、また教養としての学びや研究を通して考え抜き行動し、互いに支えあう一人の人間として自律・自立していくための礎となる足跡(そくせき)としたいものです。人と共に生きる人間力を、多角的に自分のものとして欲しいと思います。そして、その仲間が次第に増し共に支え合うことができるようになることが、大学生としての生活の充実にも繋がっていくはずです。
巡る季節の中に一人一人の生命を重ね合わせ、これから来る季節―春夏秋冬―を皆で創り出していく様を思い描きながら、共に、ここ田園調布学園大学で過ごしていきたいと思います。